-
5年生 4・5月の学級を振り返ろう 5/31
- 公開日
- 2023/05/31
- 更新日
- 2023/05/31
学年の様子
4・5月の5年1組を振り返りました。
学級目標の「メリハリ」「自分で行動」「みんなが笑顔」ができているか、点数をつけて、よかったところ、よくなかったところを出し合いました。そして、より学級目標に近づけるように、今後自分達ができることを考えました。最後に、学級目標に対する点数を出し、達成した分だけ、学級のキャラクター「たけのこくん」に色を塗りました。
さらに、レベルアップできるように、解決方法を話し合っていきます。 -
2年生 道徳「ぼくたちも仕事がしたい!」 5/31
- 公開日
- 2023/05/31
- 更新日
- 2023/05/31
学年の様子
2年生は、道徳の時間に、仕事をすることについて考えました。
自分たちの町の大人がやっている仕事を、子供であるポンタ君たちがどうしてしたのか、役割演技を通して考えました。
友達の発言から、どんどん考えをつないでいく子供たちの姿がみられました。 -
向日葵の成長が楽しみ! 5/31 389号
- 公開日
- 2023/05/31
- 更新日
- 2023/05/31
校長室
本校には、各学級ごとに広い花壇があります。美化委員会が担当する花壇も2つあり、その花壇の一部をお借りして向日葵の苗を植えさせていただきました。私は、2m位の長身の向日葵がとても好きです。真夏に職員室や校長室の窓越しに見える向日葵の花を見ていると元気が出ます。毎年枯れた向日葵の種を取って置き、種から育てています。
種から育てると、芽が出て双葉になり、そして本葉。毎日の成長がとても楽しみです。そんな思いで毎日向日葵に水やりをしていると、校務助手さんから声をかけられました。「校長先生、植えられた向日葵元気ですね。」「そうなんです。私は長身の向日葵が好きで、毎年種を取っておいて、種から育てています。ただ、青虫が本葉を食べに来るので防虫剤をかけるタイミングが難しいのです。よろしかったら、余った向日葵の苗を家へお持ちください。」「有難うございます。でも、校長先生虫除けだったら防虫剤より籾殻を株本に敷いておく方がいいですよ。籾殻を敷いておくと虫が土の中から葉へと登っていけないので。籾殻は最近、手に入りにくいので、私家から持ってきますよ。」とのこと。
翌日、校務助手さんは早速家から籾殻を一俵持ってきてくださいました。そういえば、昔母が畑の野菜の株本に籾殻を敷いていたのを思い出しました。一方父は、消防署に通報されない早朝未明に籾殻を送風機で風を当てながら、燃焼させ籾殻くん炭を作っていたのを思い出しました。私も真似をしてみたのですが、籾殻を灰色の灰にしないで、黒いくん炭にするのは、とても難しく職人技でした。
もみ殻の使い道と効果について、インターネットで調べてみました。
籾殻は、土壌改良剤として土壌にすきこむことができ、水捌けが良くなり、土壌が柔らかくなる効果があります。また、地表面に堆積させると、日差しを遮り、防草効果があるほか、地表面からの水分蒸発を抑制し、保湿効果がある。ハウス等では保温効果を期待できます。生の籾殻を畑で土の表面に敷き詰めることで、雑草や病害虫の抑制や、水分の蒸発を防ぎ土壌を保温・保湿することができます。籾殻は肥料成分はほとんどなく、分解がとても遅いため、そのまま使っても作物に影響を与えませんが、通気性が良くなり、保水性があります。
校務助手さんや両親等、先輩(年配)の方の知恵は素晴らしいものです。なんか、日々畑での野菜作りに精を出している両親の見る目が変わった気がします。また、貴重な知恵を教えてくださった校務助手さん有難うございました。
-
自分の健康課題を見付けて、解決できることは何だろう? 6年生 5/30
- 公開日
- 2023/05/30
- 更新日
- 2023/05/30
学年の様子
6年生の総合的な学習の時間です。自分や家族の健康課題を見付けて、今の自分にできることは何かと考えています。一人一人、自分の課題が異なるので、自分に合った取り組み方を熱心に見つけています。今後どんな取組になるのか、楽しみです。
-
1年生 スカイツリーからクルッ!5/30
- 公開日
- 2023/05/30
- 更新日
- 2023/05/30
学年の様子
1年生の体育の様子です。先週と今週、体育の実技指導の先生と前転・後転に挑戦しました。今日は後転ができるように様々な活動を行いました。まずは、脚や腰を高くあげる「スカイツリー」のポーズをして、そこからクルッとまわれば後転ができるということを知りました。また、マットを重ねて使うと後転が苦手な子も簡単に後転ができ、意欲的に挑戦していました。
-
カブトムシが大好きなS君! 5/30 388号
- 公開日
- 2023/05/30
- 更新日
- 2023/05/30
校長室
毎日のように校長室に5年生のS君がやって来ます。「校長先生、カブトムシ見に来たよ!」「どうぞ!」「見て、見て!カブトムシが完全に蛹になったよ。」「蛹はどれくらいの期間続くの?」「それぞれだけど、1箇月ぐらいかな。」「蛹になったら餌は食べないの?」「食べないよ。」「そしたら、熊の冬眠と一緒だね。」「うーん。」「何のために蛹の成長過程が必要なの?」「幼虫の時は、カブトムシの部位がドロドロながいぜ。それが、固い蛹の殻の中でそれぞれの部位が形作られるがいぜ。」「えーS君何でも知っているがね。すごーい。」「じゃーまた明日見に来るからね。さようなら。」
疑い深い私は、インターネットで調べてみました。
カブトムシは蛹になるのですか?
冬眠から目覚め、食欲旺盛で活発に活動していた幼虫が、徐々にエサを食べなくなっていきます。身体的な特徴としましては、白っぽかった体が黄色っぽくなりシワが目立つようになります。 ほとんどの場合は、4月から5月の時期にこのような状態になります。カブトムシが蛹になっている期間は約1か月。 この期間にタンパク質が組み替えられて、文字通り生まれ変わり、あのカッコいい成虫になります。 オスのツノ! 蛹になる時点でいきなり生えてきます。 幼虫は前蛹になったときに少しシワシワになります。 その時にツノになる外枠( ジェット風船をたたんだような )ができて、そこに液状の体液が流れ込むことによって、ツノになるそうです。
S君とカブトムシについて楽しい会話ができるのが日課になってきました。カブトムシの成長は「自然の神秘」が凝縮されているように思います。カブトムシの幼虫をくださった加藤さん有難うございました。(写真は校長室の飼育ケース)
-
5年生 去年の自分を超えよう! 5/29
- 公開日
- 2023/05/29
- 更新日
- 2023/05/29
学年の様子
スポーツテストが始まりました。
去年の記録を参考にして、今年の目標を設定しました。
今日は、シャトルランにチャレンジし、目標の記録を超えられるように、あきらめず走りました。待っているときも、「あともう少しで50回だよ」「がんばれ」等と、相手を励ます、あたたかい声援を送る姿が見られました。他の種目もこの調子で頑張りましょう。 -
3年生 台上前転できたよ! 5/29
- 公開日
- 2023/05/29
- 更新日
- 2023/05/29
学年の様子
3年生は、先週今週と、体育指導を受けました。
台上前転のコツ、「おしりを高く上げる」「まわる途中に足をのばす」を教わり、みんな上手にできるようになりました。 -
黒部名水マラソンに参加して! 5/29 387号
- 公開日
- 2023/05/29
- 更新日
- 2023/05/29
校長室
昨日、黒部名水マラソン10kmコースに参加しました。マラソンに参加するのは、15年ぶりぐらいですが、同僚と元同僚の2名に誘われての参加でした。この2名は、昨年の富山マラソンに参加しているので、この2名にとっては何でもない参加でした。
私にとっては、とてもハードルが高く完走できるか半信半疑でした。しかし、一緒に走ってくれた2名は、キロ6分半のペースで私を最後までリードしてくれ、励まし続けてくれました。そのおかげで、10kmを65分で走り切ることが出来ました。走り切った後の爽快感は、言葉にできないぐらいでした。高橋尚子選手も特別ゲストとして、ランナーにエールを送り続けてくださいました。
コースは、海沿いの道路が主で潮風に当たりながら、また立山連峰の景色も楽しみながらの快走でした。沿道では、地元住民が手を振って応援してくださり、背中を押していただきました。生地地区式年太鼓で大会を盛り上げていただいたり家庭料理で揚げ立てのポテトをランナーに振舞っておられるご家庭もありました。47都道府県全地域からランナーが集まり、地域一体になって心温まる歓迎をする皆さんのご厚意に感動しました。
また黒部市を訪れたいなという思いが強くなりました。11月19日に開催される「となみ庄川散居村横断マラソン大会」では、逆の立場で参加者を歓迎したいという思いになりました。私のペースに付き合ってくれた2名の同僚の皆さん有難うございました。
-
木と針金を使って、オリジナルの別荘をつくろう 6年生 5/26
- 公開日
- 2023/05/26
- 更新日
- 2023/05/26
学年の様子
6年生の図画工作科の時間です。木と金属といった異なる材料を組み合わせて、オリジナルの別荘をイメージしながら製作しています。自分の納得がいくように、試行錯誤したり、友達と相談したりしながら活動を進めていきました。
-
5年生 北海道と富山県のくらしは似てる! 5/26
- 公開日
- 2023/05/26
- 更新日
- 2023/05/26
学年の様子
まず、北海道の住宅街の写真を見ました。すると、どちらも屋根の上に雪が積もっているのに、富山県とは違って平らな屋根の家ばかりだと気が付きました。そこで、北海道の寒く雪の降る気候への暮らしの工夫を調べました。
教科書や資料集、タブレットを使って調べ、調べたことを発表しました。
北海道の家は、たくさん降り積もったときに屋根雪の心配がないようになっていることや、ロードヒーティングという道路により、道路が凍らないようになっていることなど北海道の暮らしの工夫が分かりました。
子供達からは、「富山県と似てるところがたくさんあるね。」と富山県と類似点や相違点にも気が付いていました。 -
5月として最強台風接近! 5/26 386号
- 公開日
- 2023/05/26
- 更新日
- 2023/05/26
校長室
5月としては最強クラスの台風2号が、来週前半には沖縄に接近、本州付近も前線が刺激されれば大雨の恐れがでてきました。「スーパー台風まで発達し、きのうグアムを直撃しました」というニュースが入ってきました。
きのうのグアムの映像には、強風のためか、ボンネットが壊れた車も。ホテルの一室では、床が歩くとぴしゃぴしゃいうほど水浸し。バスタブにはった水がまるで地震のように左右に揺れる。「日本では見たことのない状態です。すごい怖い」と日本人旅行客がコメントしておられます。
結婚式と新婚旅行をあわせて来たという男性は「パラセーリングやジェットスキーは全部キャンセル。きょう帰国の予定だったけど、飛行機のキャンセルが出ているので、連泊して滞在すると思います」と話しておられました。アメリカ国立気象台も「スーパー台風が接近中」と注意を促しています。
視聴者からの声として、九州への修学旅行を心配する人や、「今から食料を買い出しに行きます」という沖縄在住女性もおられました。
気象予報士の増田雅昭によると、台風2号が進む海域は「海水温が高く、台風は5月としては非常に珍しいぐらいまで発達しながら西へ向かっている」そうです。来週火曜水曜と徐々に北上し沖縄に近づくと予想されます。本州へは接近しなくても前線を形作るため、所により大雨の可能性もあるそうです。
本州への接近の可能性は低いようですが、大雨の備えは必要なようです。来週後半の天気予報に注意していきたいです。
-
4年生 筆算の計算を進められない・・・ 5/25
- 公開日
- 2023/05/25
- 更新日
- 2023/05/25
学年の様子
算数科の授業で、「86÷4」や「62÷3」の筆算の仕方について考えました。
「一の位に商が立たない・・・」
「こんなのできるの?」
子供たちは、今までの筆算との違いに気づき、一の位の商の立て方について話し合っていきました。
黒板に友達が書いたことに書き足しながら、
「一の位の商は『0』でいいんだ!」
と結論を出しました。
友達に分かりやすく伝えようとしたり、友達から学ぼうと聴いたりする姿が、とてもすてきでした。 -
2年生 ふしぎな生き物があらわれた! 5/25
- 公開日
- 2023/05/25
- 更新日
- 2023/05/25
学年の様子
図画工作科では、白いクレヨンと絵の具ではじき絵を描いてます。絵の具に混ぜる水の量や、明るい色から塗ること等に気を付けて、色付けをしました。白いクレヨンで描いた生き物が、どんどん浮かび上がって見えることを楽しんでいました。
-
大人の矛盾をどう教える? 5/25 385号
- 公開日
- 2023/05/25
- 更新日
- 2023/05/25
校長室
先日6年生の授業参観をしていると、ある男の子に尋ねられました。「校長先生、これだけ命が大切だと言われているのに、なぜウクライナでは今だに戦争を続けているのですか?」6年生ともなると、新聞やテレビでこれだけ報道されているウクライナ紛争を気にかけているのでしょう。答えるのに、戸惑ってしまう質問です。「人間は愚かしい生き物だから」「人間の欲望が引き起こす」と言っても、命の尊厳を尋ねる小学生への適切な答えになっているとは思いません。
答えられない子供からの問いかけは、矛盾した言動を我が身に問いかけることもなく見過ごしている私たち大人への戒めかもしれないと子ども家庭教育フォーラム代表の富田富士也氏はおっしゃっておられます。私たちはすべてにおいて、完全、明快にはできない不完全な存在です。そのことへの自覚を促しているのではないでしょうか。とも付け加えておられます。
私は、中学教師時代における我が子の子育てを次のように顧みます。「私は中学校教師として、進路指導の先頭に立って『脱偏差値』『相対評価ではなく絶対評価(他人と優劣を比較するのではなく個人内の伸びに着目)』を力説してきました。それなのに一方で我が息子を『受験戦争に』に駆り立てていたのです。かろうじて教員免許は取得してくれましたが、就職は民間企業の営業マン。まったく畑違いの仕事に就きました。しかし、顧客への接待を生き生き母に話す息子を見て妙な気持になります。」
これからも、子供が指摘してくれる「大人の矛盾」をごまかして返答するのではなく、誠実な気持ちで思いをぶつけ合っていけたらと思います。
-
4年生 側転への挑戦 5/24
- 公開日
- 2023/05/24
- 更新日
- 2023/05/24
学年の様子
今日の体育は、富山大学から講師の先生を招き側転の方法を学びました。前転から壁倒立、側転へとステップをふみながら練習しました。壁倒立の練習では、講師の先生から顔の向きや手の付き方など詳しく教えていただいたことで、壁倒立が出来る子供が増えました。子供たちが今日習ったことを生かして側転が出来るようになればうれしいです。
-
1年生 誰が、何をしている?5/24
- 公開日
- 2023/05/24
- 更新日
- 2023/05/24
学年の様子
1年生の国語の様子です。教科書の絵を見て、誰が何をしているかの文を考えました。「おんなのこがうたう。」や「すずめが木にとまる。」など、「〇〇が〇〇。」となるように文を考えました。学習の振り返りの時間では、「自分では思いつかなかった文を友達が言っていてすごいと思いました。」と話す子供もおり、みんなで学習する楽しさを感じている様子でした。
-
体育実技講習! 5/24 384号
- 公開日
- 2023/05/24
- 更新日
- 2023/05/24
校長室
本日、3,4年生を対象に富山大学人間発達部 准教授(体操競技部 監督)の佐伯 聡史 氏を招聘して器械運動の体育実技講習会を実施しました。3年生は、跳び箱の上での前転が出来ることを、4年生は、倒立前転が出来ることを目標にプログラムに沿って練習を行いました。倒立が出来るようにするために、目線を両手の爪を見るようにすること(頭を入れ過ぎない)や恐怖心を克服して足を2,3回振り上げることを練習をしました。子供たちは、佐伯教授がおっしゃる練習のポイントを遵守すると、1時間内にみるみる上達していくのが分かりました。佐伯教授有難うございました。
佐伯教授がゼミ内の3名の大学4年生を連れてこられました。私は、講習前の時間を利用して3名の大学生に質問しました。「これから、教員採用試験の準備をされるのですか?」「いや違います。富山大学には、教員免許を取るために入学しましたが、教員よりやりたい仕事があるので民間企業に就職します。」3人とも同じ答えでした。「皆さん出身はどこですか?」 A「埼玉県です。」、B「長野県です。」、C「兵庫県です。」 「どうして富山大学を選んだのですか?」 A「教員免許が取れることが分かったからです。」、B「富山大学は、バスケットボールの強豪なので、バスケットボールを続けたかったからです。」、C「高校まで体操をやっていて、佐伯監督が率いる体操部に入りたかったからです。(笑)」
佐伯教授に尋ねると、「最近の学生は、教員免許を取っても教員採用試験を受験しないし、教員になっても若いうちに民間企業に移ってしまう。しかし、民間企業に勤めているうちに、教員になりたくなって採用試験を受ける者もいますよ。」とのこと。いずれにせよ、教職の世界では、若い優秀な人材の確保が困難になっていることは間違いないと思います。若者が教職を敬遠する理由として遣り甲斐なのか、長時間労働なのか、処遇なのか人それぞれ理由があるようです。
一方、5月10日自民党の「令和の教育人材確保に関する特別委員会」が教員の処遇改善に向けた提言をまとめました。時間外勤務手当の代わりに支払われる月給への上乗せ分(教職調整額)について、現行の4%から10%以上への引き上げを明記。2024年度中の国会への関連法案提出を求めました。
また、提言はなり手不足の原因ともされる教員の長時間労働に関し、「状況を改善することは喫緊の課題」と指摘。小学校で約41時間、中学校で約58時間となっている月ごとの時間外の在校時間を、将来的に20時間程度に減らすよう求めました。
学級担任の負担の大きさなどを踏まえ、「学級担任手当」の創設も盛り込まれました。教員になった人には奨学金の返還を免除・軽減する策も示されました。
国も「教師が取り巻く環境を抜本的に改善し、質の高い学校教育の実現に向けて、優れた人材を得ることが不可欠」と強調してくれています。国の政策が若者たちに浸透し、教員のなり手不足解消に結び付いてくれることを願うばかりです。
-
学校だより5月号
- 公開日
- 2023/05/23
- 更新日
- 2023/05/23
お知らせ
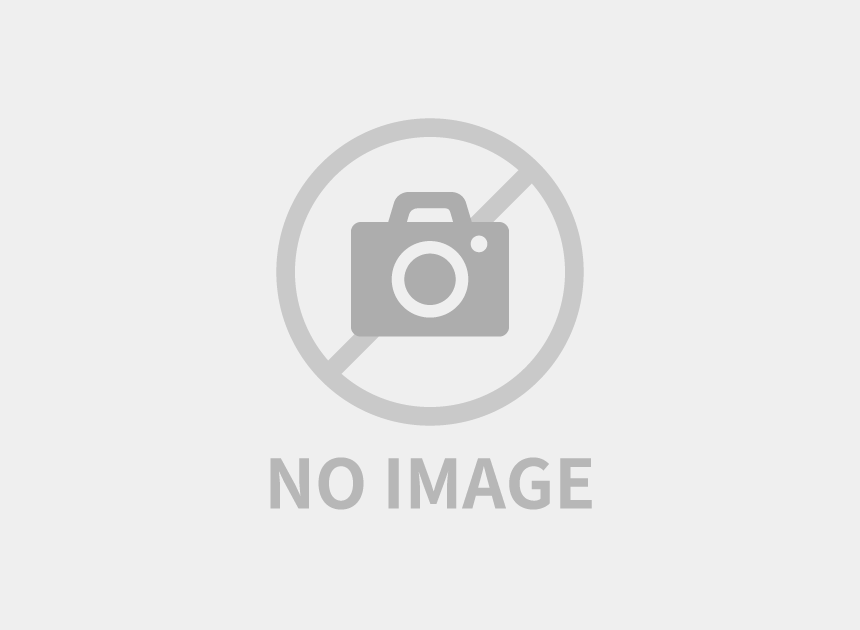
学校だより5月号をアップしました。「配布文書」をご覧ください。
-
3年生「ふしぎだな」 5/24
- 公開日
- 2023/05/23
- 更新日
- 2023/05/23
学年の様子
3年生は、「まいごのかぎ」という物語の学習に入りました。
「どうしてうさぎが最後にも出てきたんだろう。」「ふしぎ。」「ちょっとこわい。」など、子供たちは思い思いに感想を書いていました。

