-
5年生 容積って・・・? 4/28
- 公開日
- 2023/04/28
- 更新日
- 2023/04/28
学年の様子
容積の学習です。
板で囲まれた箱の中に水がどのくらい入るかを考えました。
板の厚さを考慮することが難しく悩んでいると、
「ブロックを使えば説明できるかも!」となったことから、
前回まで使用していたカラーのブロックを使用して説明を考えました。
具体的な操作があることで、子供達は容積の理解を深めていました。 -
租税教室! 4/28
- 公開日
- 2023/04/28
- 更新日
- 2023/04/28
学年の様子
6年生は、砺波市役所税務課辻さんから税金の役割について学びました。税金がないと消防や医療、社会保障がなくなることを理解し、税金の大切さについて考える機会となりました。また、準備していただいた1億円の模擬札束(1万円札約10kg分)を持ってみることにより、税金の金額の大きさに驚いていました。子供たちは、歓声を上げながら模擬札束を持ち上げていました。
-
少年消防クラブ入隊式 4/28 369号
- 公開日
- 2023/04/28
- 更新日
- 2023/04/28
校長室
本日、少年消防クラブ入隊式を実施しました。宮脇幹事長様はじめ3名の幹事長さん及び加藤砺波消防署長さんはじめ3名の所員さんにご来校いただきました。
私は、次のような挨拶をさせていただきました。
6年生の皆さん「少年消防クラブ入隊」とは、どのような意味を持つのか一緒に考えましょう。火災に関する知識を身に付け、自分たちの周りから火災を出さない環境を作ること、火災を予防すること。これらを皆さんが中心となって家族や近所に推進して欲しいのです。
具体的にどんな行動をとればよいでしょうか。例えば、家族で出かける前に「家の火元の点検大丈夫かな?」「暖房機の近くにこんな燃えやすいもの置いて大丈夫かな?」「コンセント付近に埃が溜まっているけど大丈夫かな?」「近所で焚火をしておられるけど大丈夫かな?」・・・等こんな声が皆さんから挙げて欲しいのです。(途中略)
最後に、代表の児童に続いて誓いの言葉を6年生全員で言いました。
「私達は火災予防の知識を身に付けます」
「私達は火の元の点検を励行します」
「私達は市民に防火の心を伝えます」
「私達は火災のない街づくりに努めます」
「私達は火遊びや焚火をしません」
消防署長さんに伺いますと、近年は県内・市内とも火災の発生件数が大きく減っているそうです。しかし、全国では、火災の大勢の人が亡くなる事案も発生しており、県内・市内でもこのまま推移して欲しいとのこと。
私は、今から44年前(当時高校1年生)の4月11日15:47に発生した福光大火が忘れられません。製材所の2階付近から出火し同工場を全焼。その後近隣の日本抵抗器福光工場などの工場などにも延焼し、やがて小矢部川沿いの民家にも延焼範囲が拡大。当時この一帯は木造住宅が密集していたこともあり、大火となりました。
当日は南西の風8 〜15メートルの医王山おろしの強風が吹いており、湿度も35%しかない春先のフェーン現象の状態でした。焼損件数は全焼42世帯、半焼15世帯、計57世帯の被害となりました。幸いにも軽傷者はいましたが、死者は出ませんでした。
火災発生時間は、私は高校から帰宅途中で、城端線の汽車に乗っていました。医王山の麓方面からもの凄い煙が上がっていました。福光駅に到着すると、至る箇所から炎が上がっているのが見え、大火だとすぐに分かりました。我が家が風上にあることを確認した後、中学の同級生宅が延焼に遭いそうなことに気付きました。同級生宅には、まだ火の粉は上がっていませんでしたが、万一に備え家財道具を運び出すのを手伝いました。残念ながら、同級生宅は全焼でした。
フェーン現象が起こりやすいこの季節を迎えると毎年福光大火を思い出します。人の命や財産を一瞬にして奪う火災は、本当に恐ろしいです。今日入隊した6年生の子供たちが、火災予防に少しでも貢献してくれることを祈るばかりです。
-
BFC入隊式 6年生 4/28
- 公開日
- 2023/04/28
- 更新日
- 2023/04/28
学年の様子
6年生はBFC入隊式を行いました。火災予防の大切さについて考える機会となりました。これからは、少年少女消防隊として、学校や家庭、地域の人たちへ防火の心を伝える意識を高めました。(校長室参照)
-
2年生 1・2年なかよく学校探検!
- 公開日
- 2023/04/27
- 更新日
- 2023/04/27
学年の様子
2年生が1年生を学校探検に連れて行きました。
学校中をまわり、いろいろな教室の紹介をしました。1年生と楽しく交流できて、とても満足そうでした。これからの1年生との活動が楽しみです。 -
どんなことにもあきらめず挑戦〜あったか言葉で協力し合う庄南っ子〜4/27 368号
- 公開日
- 2023/04/27
- 更新日
- 2023/04/27
校長室
本日運動会結団式を行いました。「どんなことにもあきらめず挑戦〜あったか言葉で協力し合う庄南っ子〜」は、子供たちが話し合いで決めた運動会テーマです。
結団式では、初めに団役員の自己紹介があり、続いて団長から運動会テーマの説明がありました。団長は、説明原稿が準備されていたとはいえ、実に分かりやすくテーマの説明をしていました。
それが終わると、6年生が下級生に応援の振り付けや歌の指導を始めました。6年生は、相当に練習がしてあるらしく、歌詞や振り付け説明書を見ずに下級生に手本を見せていました。また、初めて練習を行う下級生に親切丁寧に教えていました。
この光景を見ていた私は、子供たちが主体となる特別活動においては「教師は、本番前の仕掛けをいかに行うか」「本番では教師は、どれだけ口出しを我慢できるか」が大切であることを再認識しました。まさに、テーマの通りの活動を実践しているなと思い、嬉しい気持ちになりました。
-
1年生 いろいろなものの数を数えよう 4/26
- 公開日
- 2023/04/26
- 更新日
- 2023/04/26
学年の様子
1年生の算数の様子です。算数セットを使って、数を数えるゲームをしました。提示された絵の数をブロックで表したり、提示された数字を数図カードで表したりして、1〜5の数に親しみました。ゲームが進むにつれて、どんどん反応が速くなっていきました。
-
4年生 外国語活動 自己紹介をしよう 4/26
- 公開日
- 2023/04/26
- 更新日
- 2023/04/26
学年の様子
外国語の時間に、自分の好きなものや嫌いなものを友達やALTのニコール先生に「I like〜」や「I don`t like〜」を使って紹介しました。子供たちは緊張していましたが、上手に自己紹介をすることができました。
-
筍の豊作の表年と不作の裏年?4/26 367号
- 公開日
- 2023/04/26
- 更新日
- 2023/04/26
校長室
先週の日曜日の朝に、母の実家が所有する竹林に筍の収穫に出かけました。筍は、冷凍して保存食にも出来るため、我が家では1年中、食卓に並んでいます。昨年は、5回ぐらい出かけて、計100kg収穫したでしょうか。我が家では食べ切れず、職場や親戚、知人に裾分けをしました。ところが、今年は全くといって穫れないのです。1時間余りへとへとになる位竹林を歩き回りましたが、収穫できたのが僅か6kgでした。この分は心待ちにしている県外の知人に、そのまま郵送しました。
筍は、どうして豊作の年と不作の年では、収穫量がこれだけ違うのでしょうか。インターネットで調べてみました。
一般的に、農作物はその年の天候が良いか悪いかで、豊作か不作かが決まるのですが、筍については天候とは関係なく、ほぼ1年ごとに豊作の「表年(おもてどし)」と不作の「裏年(うらどし)」が繰り返されています。
筍は、豊作年を「表年」といい、逆に不作年のことを「裏年」といいますが、何が原因で豊作不作が起きるのでしょうか。
林野庁の公式サイトに載っている「竹の性質」によれば、竹は3〜4年目の地下茎が最もたけのこを産み、5年目を過ぎると減少し、豊作(表年)と凶作(裏年)がおおむね隔年にあらわれ、たけのこの発生量に差が生じるとのことです。
これについては、竹の葉の新芽と落葉のサイクルが関係するという説もあります。新芽が光合成で作った糖は根に蓄えられ、多くのタケノコを成長させます。したがって、その年は豊作で「表年」になります。
ところが、それらの収穫後は、葉がさほど落ちず、新しい葉もあまり出ないので光合成もさほど行われず、根に蓄える糖も少なくなります。その結果、タケノコが少なくなるので、その年は不作で「裏年」になります。
最盛期の勢いがなくなると、波動砲やかめはめ波のようにエネルギーの放出と充填を交互に繰り返すというイメージです。ただ、ここで不思議なことに気がつきます。よく、テレビや新聞などで「金沢の筍、今年は表年!」とか報道されますが、どうして個々の筍の豊作や不作が同調するのかという疑問が起こります。
金沢の別々な場所で、別々の時期に植えられた竹なのです。個々のタケノコの隔年現象なら、結果はランダムというかバラバラですから「表年」も「裏年」もバラバラなので、竹林全体でも地方全体でも平均化され、安定した収穫が得られるはずです。それなのに、何故、「金沢の筍、今年は表年!」となるのでしょう?これは、「同調」という現象で、生理学的説明では説明できず、まだ明確に解明されていない現象の1つらしいです。
昔から美味しく食べている筍でさえ、まだ解明されていない現象をもっているなんて、この世は本当に不思議なことだらけですね。筍の「表年」と「裏年」の出荷量にはどれくらいの差があるのでしょうか?
金沢市の公式サイトによれば、平成24年度から平成29年度のタケノコの出荷量は次のようになっています。
平成24年度:866t
平成25年度:245t
平成26年度:692t
平成27年度:252t
平成28年度:626t
平成29年度:220t
筍農家さんとしては、毎年できるだけ安定した収穫を目指したいと思いますが、表年と裏年では2〜4倍の収穫量の差があるみたいです。時々、筍に白い粉が付いているのを見たことがありませんか?カビと間違える人もいますが、これは「チロシン」と呼ばれるアミノ酸で食べても無害です。
チロシンは時間が経つとアクの成分に変化しますので、たけのこを収穫したらすぐにお湯に通したほうがよいです。もし、時間が経ってしまったなら、下ゆでしてアク抜きをすればOKです。
今年も旬の筍を刺身や味噌汁、炊き込みご飯で賞味させていただいています。貴重な筍を十分味わって食べたいと思います。
-
新しい実験器具を使ってみよう! 4/25
- 公開日
- 2023/04/25
- 更新日
- 2023/04/25
学年の様子
6年生の理科の授業の様子です。物の燃え方について学習しました。瓶の中気体の割合を調べるために気体検知管の使い方を一人ずつ触って確かめながら理解していきました。
-
3年生 話合いは楽しいな 4/25
- 公開日
- 2023/04/25
- 更新日
- 2023/04/25
学年の様子
3年生は、国語で「きつつきの商売」という物語を読んでいます。
動物たちの「したこと」「言ったこと」「様子」から、登場人物の気持ちを考えました。そして、分からない部分を友達に聞いて、読みを深めていました。 -
加藤さん有難うございます!4/25 366号
- 公開日
- 2023/04/25
- 更新日
- 2023/04/25
校長室
昨日知人の挽物職人加藤秀明(78)さんが来校され、カブトムシの幼虫を水槽に4杯いただきました。全部で50匹位の幼虫でしょうか。2年前に初めて本校に持って来ていただき、それを大切に育てていた3年Y君が今年も待ち遠しくて加藤さんに直接依頼したことを受けてのことでした。Y君を中心とした男子3名は、加藤さんが桶に入れてこられた幼虫の入ったおが屑の混じった土を手で水槽に移しました。子供たちは、カブトムシが本当に好きなようで作業中の子供たちの目は輝いていました。
カブトムシの飼育ミニ知識です。カブトムシの幼虫は、季節と共に変化していきます。 夏(卵)→秋〜春の終わり(幼虫)→初夏(サナギ)→夏(成虫)といった感じに成長していきます。カブトムシの幼虫には弱点があります。それは、直射日光と寒さと水分不足です。途中で死んでしまう場合は、次のどれかが原因の時が多いです。それぞれの対策は以下の通りです。
•直射日光:日陰の涼しいところに置く
•寒さ:昆虫マットを深めにする
•水分不足:まめな霧吹き
それと昆虫マット(腐葉土)が不足するとまれに共喰いすることもあるようですので、昆虫マットは適度に交換するようにします。
加藤さんは、挽物作りの作業で出た欅のおが屑を腐葉土と混ぜ合わせ、そこにカブトムシの雄と雌の成虫を入れ産卵をさせておられます。幼虫に育った今頃の季節に、市内のこども園等に配付され、幼い子供たちを喜ばせておられます。
お届けいただいてこれで3年目になりますが、1年目は成虫になる前に8割ぐらい、2年目は半分ぐらい死んでしまいました。今年は、全部成虫になるよう子供たちと知恵を出し合い飼育していきたいと思います。加藤さん有難うございました。
-
5年生 体積を求めよう。 4/24
- 公開日
- 2023/04/24
- 更新日
- 2023/04/24
学年の様子
前回は、箱の体積をどのように求めるか、ブロックを使って考えました。
今日は、その学びを生かして立体の体積を求める練習問題に取り組みました。
いくつかのレベルの中から、自分に合ったレベルの問題を選んで解きました。
早く合格まで到達した子供は、悩んでいる子へ駆け寄り、印をつけながら分かりやすく教えてあげる姿が見られました。 -
2年生 たし算のきまりは何だろう? 4/24
- 公開日
- 2023/04/24
- 更新日
- 2023/04/24
学年の様子
2年生の算数では、たし算のひっ算をしました。
たされる数とたす数を入れ替えても、答えが同じになるというきまりを見付けました。そして子供たちは、見付けたことを友達に詳しく説明していました。 -
令和5年度 受賞の記録
- 公開日
- 2023/04/24
- 更新日
- 2023/04/24
お知らせ
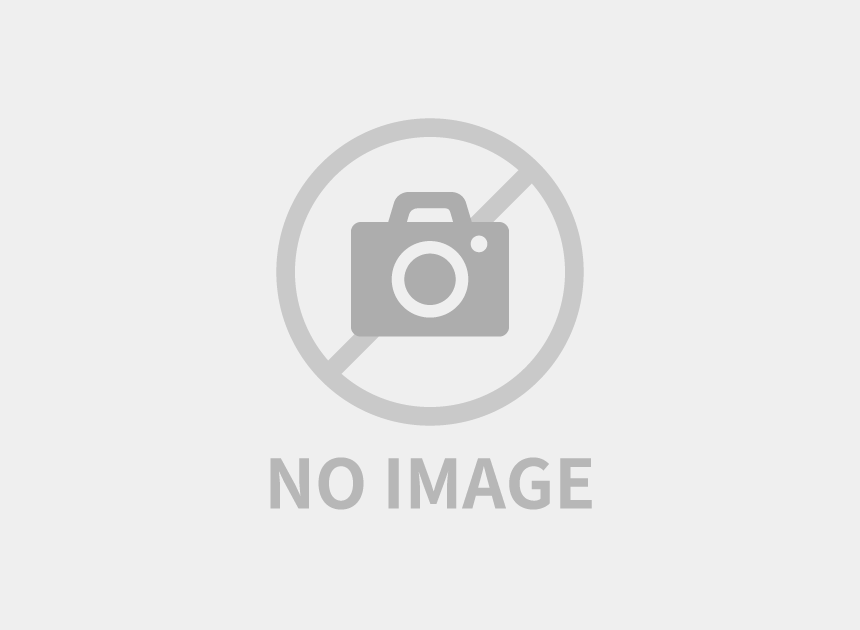
4月24日付けの受賞報告をアップしました。
-
令和5年度 受賞の記録
- 公開日
- 2023/04/24
- 更新日
- 2023/09/06
受賞
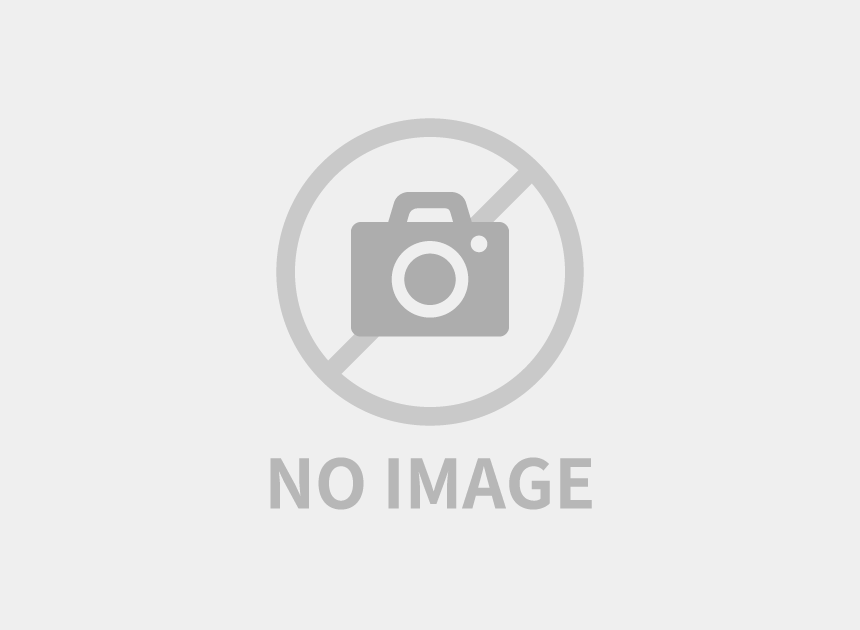
3月25日 第32回高岡ケーブルテレビ杯高岡市ジュニアオープン
バドミントン大会 小学1年シングルスの部 優勝 横山千栞
4月23日 第33回砺波市スポーツ少年団交流大会バドミントン競技
3年女子シングルス 2位 横山千栞
4年女子シングルス 3位 金平浬央
4年女子ダブルス 2位 金平浬央、飯田倖鈴
5年男子シングルス 3位 今井聖也
-
高岡のプール男児死亡!4/24 365号
- 公開日
- 2023/04/24
- 更新日
- 2023/04/24
校長室
痛ましいプール死亡事故のニュースが飛び込んできました。22日夕に高岡市木津の「オーパスフィトネスクラブ高岡」のプールで、保育園児笠谷拓杜ちゃん(5歳)が沈んでいるのが見つかり、その後死亡が確認されました。プールに設置された監視カメラの記録では、拓杜ちゃんが溺れてから沈んでいるのが見つかるまで約5分かかっていたことが分かったようです。
園児は万一に備えてヘルパー(救命具)を腰に付けることになっていたようですが、救命具の紐は拓杜ちゃんの身体から外れていたようです。水深は110cmで、身長の低い園児のためにプールフロアを敷かれていたようですが、拓杜ちゃんが飛び込んだ際にフロアから足を滑らせたようです。最悪が重なって起こった事故のようです。
本校でも、6月から水泳学習が始まります。これを機に指導体制の強化を図り、事故が絶対に起こらないように万全を期していきたいと思います。
私事になりますが、2人の息子が小学校時代に私が居住する(福光広瀬)地区では、研修旅行が夏休み中に実施されていました。保護者の代表が地区の子供たちを連れて1泊研修に出かけるというものでした。息子たちの代は、行き先に国立能登青少年交流の家が選ばれていました。参加した1年目のことです。子供たちは、プールで泳いだり浜辺で海水浴をしたりして楽しんでいました。
その時思いました。保護者の代表が子供たちを見るといっても自分の子供ばかりを見ておられます。広瀬地区全員の子供を見ようと思っても、他のたくさんの子供が入り混じる中で把握するのは絶対に不可能です。一緒に行った私は、事故が起こらないかはらはらしていたのを覚えています。そこで、次年度からは水泳(水浴び)を行わない活動にするよう提案しました。根拠を丁寧に説明すると皆さんに納得していただけました。
話は変わりますが、20年程前に私は事故ではなく病気で、当時15歳の姪を亡くしました。子供が親より先に亡くなることは、親族にとってやりきれないものです。当時は、「姪の病気は、本当に治せなかったのか」と医学も恨みました。葬儀中に大勢の参列者からすすり泣く声が響き渡ったことは、今でもはっきり覚えています。
交通事故、水の事故等悲惨な事故が後を絶ちません。子供たちの大切な命を預かっているという認識を強く心に刻んで、学校教育活動に取り組んでいきたいと思います。
-
学校だより
- 公開日
- 2023/04/23
- 更新日
- 2023/04/23
お知らせ
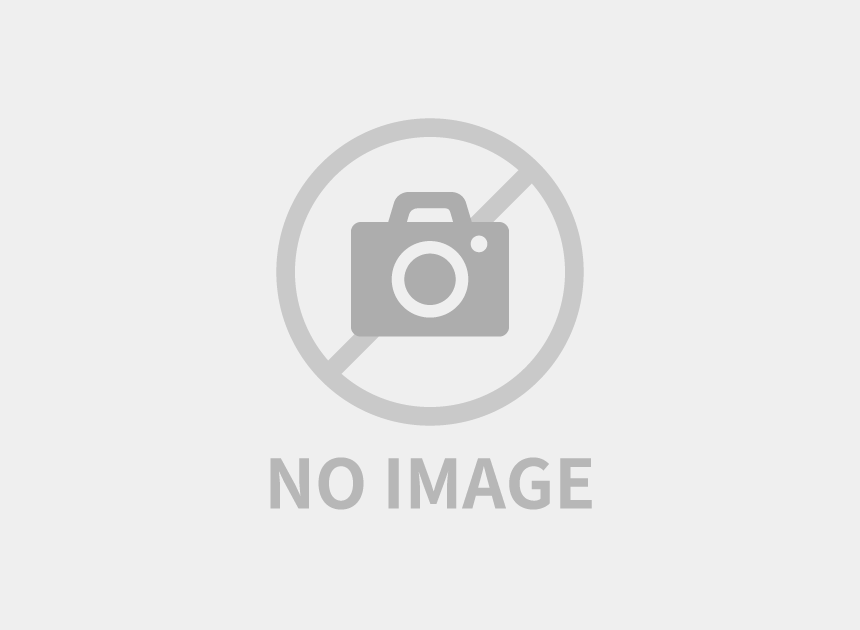
学校だより4月号をアップしました。「配布文書」をご覧ください。
-
庄川はどこから流れてくるのかな? 4/21
- 公開日
- 2023/04/21
- 更新日
- 2023/04/21
学年の様子
4年生の社会の授業の様子です。地図を見ながら庄川がどこからどこへ流れているのか調べました。庄川が思っていたより長い川ということに驚いていました。
-
令和5年度 受賞の記録
- 公開日
- 2023/04/21
- 更新日
- 2023/04/21
お知らせ
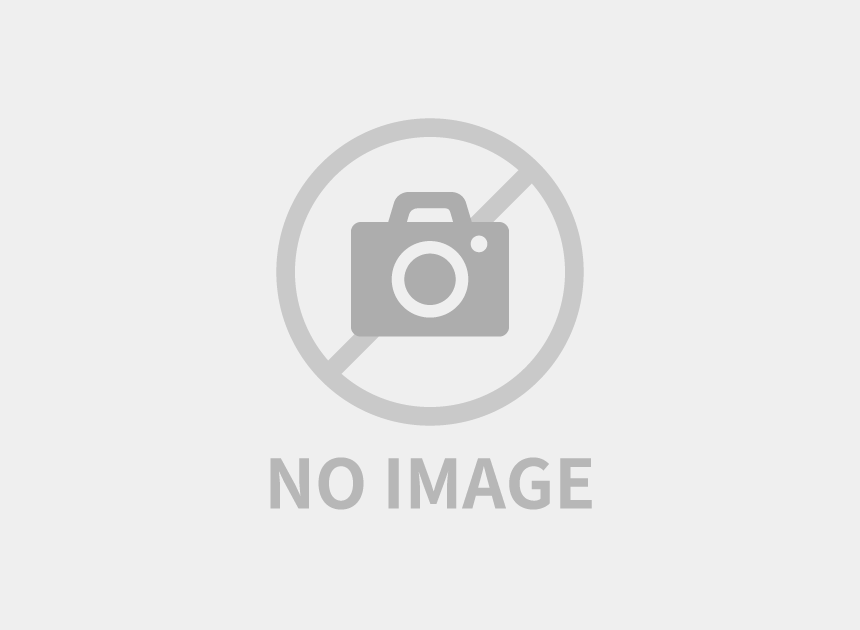
4月21日付けの受賞報告をアップしました。

