-
4年生 道徳科 家族のことについて 1/31
- 公開日
- 2024/01/31
- 更新日
- 2024/01/31
学年の様子
今日の道徳は、『ドラえもん』の中に出てくる「ぼくが生まれた日」の話から、家族のことについて考えました。授業では、パパとママに叱られたときの、のび太君の気持ちを考えたり、のび太君が生まれたときの家族の様子から、のび太君の気持ちはどのように変わったのかを考えたりしました。さらに、家の人からの手紙を読み、これから家族のために何をしていくのかを考えるときに、子供たちは、「勉強をかんばる」や「お手伝いをする」などをふりかえりに書いていました。子供たちは、家の人からの手紙を読んでいるとき、真剣に聞いていました。
4年生の保護者の皆様、お忙しい中、手紙を書いていただきありがとうございました。 -
5年生 自分の好きな季節を伝えよう! 1/31
- 公開日
- 2024/01/31
- 更新日
- 2024/01/31
学年の様子
今日の外国語の様子です。
ペアで自分の好きな季節について伝える活動をしました。
クリスマスや夏休みなどの行事をもとにその季節が好きな理由も説明します。
ALTのニコール先生にも聞きながら、英語での表現を学びそれを話すことで自分のものにしていました。
-
睡眠、6時間未満が4割 過労死白書、労働者1万人調査 1/31 514号
- 公開日
- 2024/01/31
- 更新日
- 2024/01/31
校長室
日本人は「休み下手」と言われます。休むことに後ろめたさを感じたり、休んでいても仕事のことが頭を離れなかったり。かつて「働け、働け」という時代がありました。親や祖父母ががむしゃらに働いて日本の高度経済成長の礎を築きました。私は、幼少期に両親が休んでいる姿を見たことがありませんでした。日中両親は、農作業。それに加え、父は夜も農作業や縄を編んでいました。一方母は、朝夕は家事、就寝前はセーターをほどいて、子供の成長に合わせてセーターの編み直しをしていました。居間でテレビを見たり休憩したりする姿は殆ど見たことがありませんでした。そんな中で育った私は、小学校低学年の頃から農作業を手伝うのは当たり前になっていました。
その勤勉さがいつの間にやら、ろくに休みも取らずに長時間働く悪習へと変質しました。「働き過ぎ」と海外からも批判された時期を何度か経ながら、改められずに現在に至っているように思われます。過労死・過労自殺の現状を分析した「2023版 過労死白書」が実態調査を踏まえて次のように言っています。
労働者約1万人を対象とした大規模な睡眠の実態調査を実施。45・5%は睡眠が6時間に満たないと回答した一方、62・5%が理想は7時間以上と考えており、隔たりが目立ちました。 睡眠不足に陥ると肉体の疲労が回復せず、精神にも悪影響が見られます。日本の労働者の多くは自身が理想とする睡眠時間を確保できていない。さらに、理想と実際の睡眠時間の差が大きければ大きいほど、精神状態が悪化する傾向にあると。
本校の職員室は、5時半頃になると半分位の教職員が退勤しています。我が子を保育所に迎えに行ったり、夕飯の買い物にに行ったり等様々です。しかし、それが当たり前の雰囲気になっていることが有難いです。過労問題は、超過勤務時間だけでなく質的な問題も多く含まれていると思いますが、教職員が互いに労ったり助け合ったりする雰囲気を醸成し、同僚性が高められたらと思っています。読者の皆さんは、理想の睡眠は取れていますか。(私は、あまり悩まないタイプなので大丈夫?(笑))
-
家庭教育・子育て啓発資料「小学生の理解のために」について(案内)
- 公開日
- 2024/01/31
- 更新日
- 2024/01/31
お知らせ
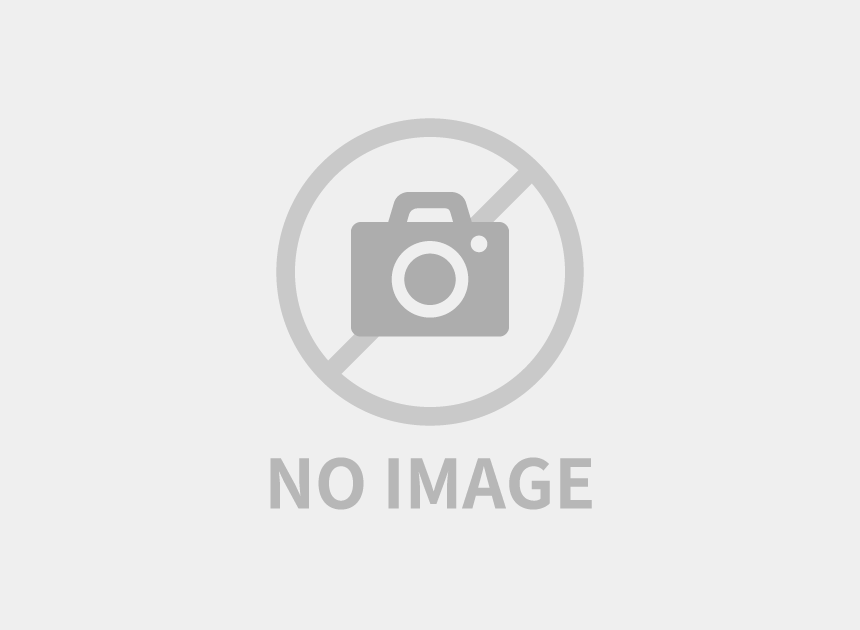
この度、富山県教育委員会より、
家庭教育・子育て啓発資料「小学生の理解のために」の作成、ウェブへの掲載がありました。富山県教育委員会、学校としましては、これからも、家庭と学校とが互いに手を取り合って子供の理解を深めていきたいと考えております。
本資料が、保護者の皆様にとって家庭教育の一助となれば幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
URL https://www.pref.toyama.jp/documents/36237/syougakuseinorikai.pdf
(※本ホームページ「リンク」からもご覧になることができます。) -
校長室へ結果報告(砺波東部ミニバス) 1/31
- 公開日
- 2024/01/31
- 更新日
- 2024/01/31
お知らせ
47回富山県春季ミニバスケットボール大会で、見事、準優勝を勝ち取った砺波東部ミニバスチーム所属の児童とコーチの方などが、校長室に報告に来てくれました。
熱心に練習をし、チームワークよく戦った成果が結果に結びついたことと思います。
おめでとうございます。
3月に、北信越大会(長野県)に出場とのことで、さらなる活躍を期待しています! -
1年生 すききらいしないでたべよう 1/30
- 公開日
- 2024/01/30
- 更新日
- 2024/01/30
学年の様子
1年生は、学活の時間に苦手な食べ物をどうすれば食べられるのかを考えました。まず、養護教諭の話を聞いて、すききらいをして偏った食事をしていると元気な身体がつくれないことを知りました。そして、苦手な食べ物をどうすれば食べられるか考えると、様々なアイディアをタブレットに記入していました。
苦手な食べ物をすぐに食べられるようになることは難しいですが、今回の授業を機に、少しでも食べてみようという気持ちが生まれていると嬉しいです。 -
令和5年度 受賞の記録
- 公開日
- 2024/01/30
- 更新日
- 2024/01/30
受賞
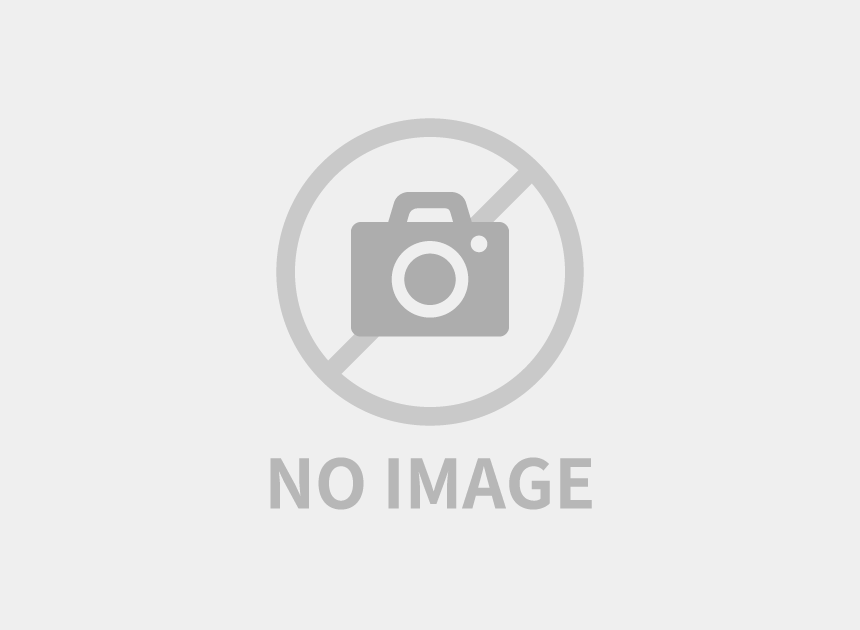
1月28日 第17回ウインターカップ フレンドリートーナメント
準優勝 庄南V・B・S
-
孤立集落の避難訓練! 1/30 513号
- 公開日
- 2024/01/30
- 更新日
- 2024/01/30
校長室
能登半島地震を受け、砺波市は9月29日に同市庄東4地区で市防災避難訓練を行うことが発表されました。孤立集落の避難訓練は、初めての実施になります。今回の地震を教訓に避難所を自動的に開設する想定震度や、冬季の災害に備えて各避難所の石油ストーブや灯油の備蓄なども検討するそうです。昨日開かれた市自治振興会協議会の席上、夏野市長さんが明らかにされたようです。
能登半島地震が起こった時、我が家では車庫の棚の上に置いておいた懐中電灯が落下し、破損しました。これを契機に懐中電灯は3個に増やし、ヒートンに紐で吊るすことにしました。今回の地震が輪島市や珠洲市では、未だに電気や水道が復旧していない地区があると報道されています。そこで、いろいろ考えてみました。まず、暖を取るために電気を使うファンヒーター以外に反射板式ストーブ並びにダルマストーブ゜はいつでも使えるようにしておこうと思います。また、電気は小電力であれば自動車のインバーター(直流電源を家庭用交流電源に変換)からとってこようと思います。さらに、水道ですが井戸が2箇所あるので、水道管が損傷しても電気ポンプで汲み上げたいと思います。水田に水を張っている時期以外は、水に汚れがなく飲料水に使えると思います。(昔は、飲料水に用いていました。)
こんなことを最近考えています。「備えあれば憂いなし」です。この災害の教訓を忘れずに日常生活を送っていきたいものです。
-
2年生 1mってどれくらい? 1/29
- 公開日
- 2024/01/29
- 更新日
- 2024/01/29
学年の様子
算数科の学習の様子です。長いものの長さの表し方を学習しました。1mがどれくらいかという感覚がつかめるように、身の回りの約1mのものを探して、ものさしで測りました。グループの人と協力して次々に測る様子がみられました。
-
漁師は津波に向かった!(沖出し) 1/27 512号
- 公開日
- 2024/01/29
- 更新日
- 2024/01/29
校長室
昨日の富山新聞に衝撃的な記事が載っていました。
1日の地震で大津波警報が発令された後、珠洲市の蛸島漁港から走る船があった。同市野々江町の漁師濱野慶弘(66)さん。多くの住民が高台を目指す中、自らの漁船に被害が出るのを防ごうと、あえて海を目指した。波にのまれ、転覆する恐れもある危険な方法だが、濱野さんは「船は漁師の命。迷いはなかった。」と振り返った。
地震発生直後、停泊中や操業中の漁船を沖合へ動かすのは「沖出し」と呼ばれる。水深が深く、海面上昇の影響が小さい沖合へ移動させることで津波をかわす手法だが、波に巻き込まれたり、移動中に転覆、沈没したりするリスクもある。
東日本大震災では実際に命を落とした人もおり、水産庁は沖出しを原則として禁じている。濱野さんも危険性は認識していたが、「船がなくなったら生活できんようになる」との思いが勝ったという。
1日の地震発生時、妻の制子(54)さんとともに自宅で正月を過ごしていた濱野さん。揺れが収まるのを待ち制子さんに高台へ逃げるよう伝えた。「あんたはどうするの?」。制子さんの問いかけに濱野さんは、「港に行く。船と心中や」と答え家を飛び出した。(途中略)
濱野さんの取られた行動は、決して肯定できるものではないと思います。残された奥さんはどんな思いでご主人の帰りを待っておられたのでしょうか。しかし、私は「漁師にとっての船」「漁業は命がけ」という点で考えさせられるものがありました。今後お魚を頂くときには、こんな漁師さんの思いを忘れないようにしたいものです。
-
3年生 友達の感想と比べよう 1/29
- 公開日
- 2024/01/29
- 更新日
- 2024/01/29
学年の様子
3年生は国語科で「ありの行列」の学習をしました。
今日は、友達の感想と自分の感想を比べました。
「友達はウイルソンのすごさに気付いていたり、ありの行列の実験の内容について感想を書いていたり、注目している部分が違う」
「感想が似ているけど、理由が違う」
等、様々な感想をもったようでした。 -
日本海側に大雪をもたらす「山雪型」と「里雪型」の違い 1/26 511号
- 公開日
- 2024/01/26
- 更新日
- 2024/01/26
校長室
3日連続の降雪となりました。私は、雪が降ると除雪のため朝4時に起きます。我が家→公民館→在所の独居老人宅→南砺市広谷(イオックスアローザスキー場入口)の親戚宅(1人暮らし)→南砺市城端金戸の親戚宅(1人暮らし)の順に除雪機のオペレーターをしています。これで2時間コースです。除雪機といってもそれぞれの場所にバケット付きのトラクターかフォークリフトが置いてあります。大型特殊免許やフォークリフト作業免許は持っています。今朝、我が家(南砺市開発 旧福光高校付近)の前の県道は除雪車が走りませんでした。しかし、南砺市広谷や南砺市城端金戸は新雪が20cm以上あり除雪車が走っていました。ここでふと「一昨日は里雪型だったのに、昨日と今日はなんで山雪型なんだ?」という疑問を感じました。早速ネットで調べてみました。
主に山沿いや山間部で雪を降らせる山雪型の時は、天気図が上の図のようになっています。等圧線は南北に伸び、まるでスイカのような縦じま模様が出現。等圧線が混み合っているところは風が強いので、日本列島は強風に見舞われます。また、寒気に注目すると、中心部分が日本海の北部あたりとそこまで南下していません。一方、海岸沿いや平地で雪を降らせる里雪型の時の天気図は、等圧線がぐにゃぐにゃと曲がっています。風は比較的弱いですが、問題は寒気です。寒気の中心が日本海の中部や南部にまで南下してきます。
積乱雲がどこで発達するかが鍵
山雪型と里雪型では雪が降る場所が異なりますが、その理由は積乱雲にあります。山雪型の場合、強い風とともに西の大陸からやってきた冷たい空気が、日本海上で水蒸気を蓄え積雲となります。この積雲が山にぶつかることで上昇気流が生まれ、雪雲が発達。その結果、山で雪を降らせる形となります。ところが、里雪型の場合は上空に強い寒気があることで、日本海上ですでに雪雲が発達。そのため、海岸沿いを中心に雪を降らせてしまうのです。里雪型は人が多く住むところに雪をもたらすため、特に注意が必要です。
雪が降ると、本校の子供たちは築山のそり遊びで大喜びです。しかし、30cm位の築山の積雪は、あと何日もつか分かりません。私としては、里雪型が有難いのですが、読者の皆さんは山雪型を好まれますか?
-
雪遊びを楽しもう! 6年生 1/25
- 公開日
- 2024/01/26
- 更新日
- 2024/01/26
学年の様子
6年生で雪遊びを行いました。まずはグループで雪だるまづくりです。なかなか大きな雪だるまができず、苦戦しながら作っていましたが、友達と協力して最後は完成を目指すことができました。残りの時間は、そりや雪合戦等で友達と楽しい時間を共有していきました。
-
学校関係者評価委員会 1/26
- 公開日
- 2024/01/26
- 更新日
- 2024/01/26
お知らせ
本日、午後、学校関係者評価委員会を行いました。
地域の方に授業参観をしていただきました。
そして、その後、今年度の成果と課題について、ご意見をいただきました。
子供たちの挨拶のこと、タブレットPCの学習について等、大変参考になりました。
今後の学校運営の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。 -
給食週間パート5 1/26
- 公開日
- 2024/01/26
- 更新日
- 2024/01/26
お知らせ
今日は、最終日。
「ドラゴンボール」にちなんだもの。
「ヤムチャスープ」
「ベジータサラダ」
「カニ玉のあんかけ」
1週間、毎日楽しみでした!
給食のお世話をしてくださる皆様に感謝です。 -
1年生 寒さに負けず! 1/25
- 公開日
- 2024/01/25
- 更新日
- 2024/01/25
学年の様子
1年生の体育の様子です。今日の体育館は、とても寒かったのですが、氷おにをして楽しく体をあたためました。大なわでは、8の字跳びに挑戦しています。なわに入るタイミングをつかめてきているので、この調子で頑張ります!
-
4年生 1平方メートルの広さとは? 1/25
- 公開日
- 2024/01/25
- 更新日
- 2024/01/25
学年の様子
今日は、mとcmの辺の長さが混ざっている長方形の面積を求める学習をしました。1mは100cmと同じ長さであることから、200cmを2mに直し、長さの単位を揃えて計算しました。
その後、1平方メートルの広さにクラスのみんなで入ってみて広さを実感しました。子供たちいわく、とても狭かったようです。 -
給食週間パート4 1/25
- 公開日
- 2024/01/25
- 更新日
- 2024/01/25
お知らせ
今日の給食は「ドラえもん」にちなんだもの。
「アンキパン」
「ジャイアンシチュー」
「ラザニア」(ひみつ道具「お料理ワッペン」を使って、のび太がつくったもの。)
「大根サラダ」(ひみつ道具「畑のレストラン」を使ってつくった大根を使用。)
今日は、朝から「廊下で、教室で、職員室で」話題になっていました。
※リンク「学校給食センター」も、ぜひ、ご参考にしてください。 -
宿題とは違う自主学習の5つの特徴(自主学習ノート3) 1/25 510号
- 公開日
- 2024/01/25
- 更新日
- 2024/01/25
校長室
伊垣尚人氏が主張する自主学習ノートの5つの特徴を紹介します。
1 一人一人が自分に合った学習内容を選べるため、学習に対して主体的になれる
宿題では「先生に言われたからやる」「先生に言われたことをやる」と受け身な学習態度になりがちですが、自主学習では自分で学習内容を選ぶことが出来るため、学習に対して主体的になれ、やる気も生まれます。自分に必要な学習は何かを考え、自ら選択して学んだ子と、親や先生に言われるまま受け身の学び手として育つ子とでは、思考の深さに大きな差が出ます。
2 1日の学習、1週間の学習計画について「振り返り」をしなが゜ら進めることで「学び方」を学ぶことが出来る。
自主学習では、1日の学習ごと、1週間ごと、1か月ごと等、定期的に自分の学習について振り返りを行います。その場その場で行き当たりばったりしかしていない子は、経験した学びを次の学習に活用することが出来ません。ですが自分にとって上手くいく学び方を身に付けている子は、他の学習内容に出会ったときでも、その学び方を上手に生かすことが出来ます。こうした「学び方」を身に付けることは、生涯にわたる豊かな学びを保障する力になります。
3 1冊のノートに努力が積み重ねられ「見える化」されるため、自己肯定感が高まる
自主学習では、学習したノートがそのままその子のポートフォリオとなり、1冊の宝物となります。その宝物が積み重なっていくことで自分の努力が「見える化」されるため、自分の継続力に自信が生まれ、次なる学習への意欲も高まっていきます。
4 家庭で自分から学習する習慣を身に付けることが出来る
自主学習では、「自主学習カレンダー」を作り、自ら学習する内容や目標を決めて取り組みます。自分が作った「自主学習カレンダー」に、学習した証の「〇」が増えていくことは、子供たちに継続する力を与え、自ら進んで学習する習慣が確立されていきます。
5 学ぶことが楽しくなる
新しいことを知ったり、出来るようになったり、知らない世界のことを調べたり、実験してみたりといった学びは、本来とても楽しいものです。子供時代にはこうした学ぶ楽しさをたくさん味わって欲しい。そんな願いが、この自主学習の取組には込められています。
私個人として、自分の学生時代を思い起こすと「自分に必要な学習は何かを考え、自ら選択して学んだ子と、親や先生に言われるまま受け身の学び手として育つ子とでは、思考の深さに大きな差が出ます。」や「その場その場で行き当たりばったりしかしていない子は、経験した学びを次の学習に活用することが出来ません。」は、まさしく「自分のことだ」と反省ばかりです。今後は、これまでの生産性と品質を競った社会から独自の価値を生み出す知識社会へと変わっていき、今までのやり方では解決できない問題に対応する能力が求められています。新しい学力観(令和の日本型教育)に立って子供たちの自主学習を推進できたらと思います。
-
元気な歌声が響いています 1/25
- 公開日
- 2024/01/25
- 更新日
- 2024/01/25
お知らせ
朝活動の時間。
各クラスから元気な歌声が響いてきます。
今月の歌は「ビリーブ」
6年生は、卒業に向けての歌を練習しています。

