-
高学年 チャレンジランニング大会
- 公開日
- 2023/10/31
- 更新日
- 2023/10/31
学年の様子
今日はチャレンジランニング大会でした。
天候にも恵まれ、さわやかな秋晴れの中、自分の力を精一杯出し切りました。順位やタイムの目標をたて、それに近付けるように全力で走る姿にとても感動しました。
結果ももちろん気になりますが、ゴールするまでの努力の過程を大いに褒めたいと思います。 -
チャレンジランニング大会 10/31 463号
- 公開日
- 2023/10/31
- 更新日
- 2023/10/31
校長室
秋晴れの下、チャレンジランニング大会を実施しました。低学年は600m、中学年は800m、高学年は1,000mのトラックと敷地周りを組み合わせたコースを走りました。子供たちの走り終わった様子は、目当てを達成して満足気な表情の子や逆に思うような順位が取れず悔しい表情を見せる子、疲れ果てて歩くことも出来ない子等様々でした。沿道には、ご家族の温かい声援があり我が子だけではなく、苦しそうな表情をしている子等どの子の背中も押していただいた気がします。本当に有難うございます。子供たちは、苦しい思いを克服しどの子も得るものがあった有意義な大会だったと思います。
秋といえばマラソンです。先週には金沢マラソン、11月5日には富山マラソンが予定されています。私事になりますが、最近長男が「お父さん、俺今年も富山マラソンに参加するけど来年は、お父さんの分もエントリしておこうか?一緒に走らない?」と誘いをかけてきます。「えーどうして?」と尋ねると「富山マラソンにエントリしておくと必ずそれを目標に練習を誰でもするがいちゃ。そしたら、体型変わるよ。無理にダイエットしなくても済むよ。」と言うのです。そのことを今日思い出し、全学年のレースを一緒に走ってみました。低学年の600mを2本、中学年の800mを2本、高学年の1,000mを2本走ってみました。合計は、4,800mになりますが、連続で走るよりきつかった感じがします。しかし、歯を食いしばって頑張る子供たちの姿が見られてとても有意義でした。また、天気も気温もマラソンに最適ですがすがしい思いになりました。
以前にも述べましたが、私は走ることが日常化しています。中学の野球部時代に毎日練習終了後に、チームで10kmを走る生活を1年間続けました。当時は、完全下校時刻がなく、顧問の先生も「来んもん」だったので、練習後に約40分間走り続けました。荒天の日は体育館の下の150m走路を走りました。このことが、次年度の大会結果には繋がりませんでしたが、良かったことが2つありました。1つは、それ以来接骨院に全く行かなくなったことです。捻挫など足の怪我は一切しなくなりました。もう1つは今まで出来なかった投手を高校・大学時代と出来るようになったことです。下半身が安定し、体重移動がスムーズに出来るようになったことから、ボールが伸び制球力が抜群についたということです。
子供(中学生含む)たちを指導していて思うのは、走った成果がすぐに見えないことが辛いなと感じています。私の場合で、2,3年経ってから目に見えるようになったように思います。
子供たちも大会の名称のように来年の大会に向けて、日々のランニングをチャレンジ(積み重ね)していって欲しいと思います。
-
3年生 チャレンジランニング大会 10/31
- 公開日
- 2023/10/31
- 更新日
- 2023/10/31
学年の様子
今日はついにチャレンジランニング大会本番!!!
スタート前は、緊張した表情のお子さんが多かったです。
1人1人の力を出し切りました。
「本番では練習より9秒もタイムが縮まったよ」
と、教えてくれたお子さんもいました。すごいですね。
ご家庭でも話を聞いてあげてください。 -
2年生 かけ算九九にチャレンジ! 10/30
- 公開日
- 2023/10/30
- 更新日
- 2023/10/30
学年の様子
2年生の算数科の学習の様子です。かけ算九九の学習が始まっています。今日は2の段のきまりを見付けました。かける数が1増えると、答えが2ずつ増えることに気付いていました。前回5の段で学習したことを生かして自分の考えを発表したり、友達の考えを聞いて思ったことを話したりする様子がみられました。
-
令和5年度 受賞の記録
- 公開日
- 2023/10/30
- 更新日
- 2023/10/30
受賞
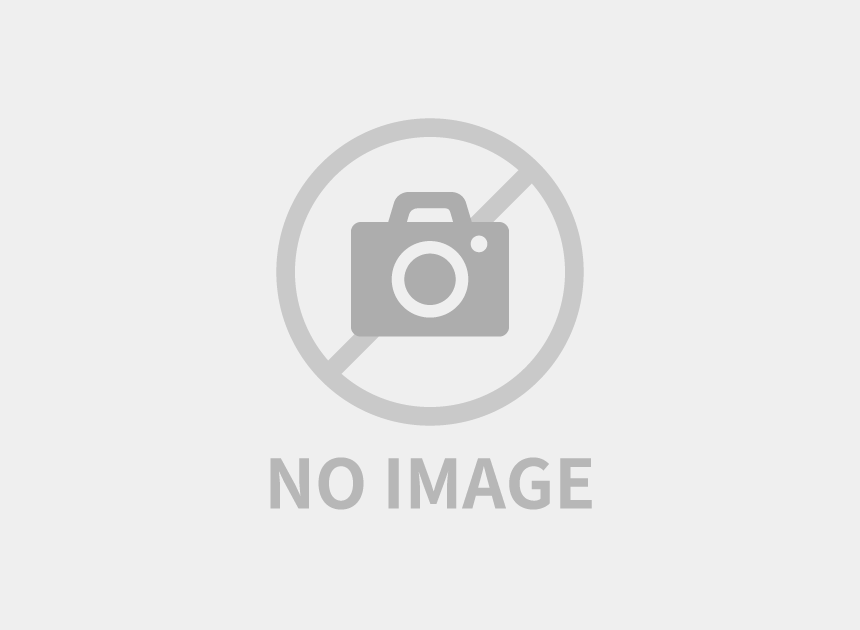
10月15日 2023年バスティンピアノコンクール富山地区予選
カテゴリー4 奨励賞 島田 聖音
10月15日 第16回 NOAHーCUP関西ジュニア空手道選手権大会
小学5年男子 初級 準優勝 高島 碧
10月22日 第44回秋季学童選手権大会
次勝 砺波東部庄南野球スポーツ少年団
10月25日 第82回富山県科学展覧会
創意工夫賞 山原 ひまり
10月29日 第9回砺波市ランキングサーキット
3年以下女子シングルス 3位 横山 千栞
4年女子シングルス 3位 金平 浬央 飯田 倖鈴
4年以下女子ダブルス 次勝 金平 浬央 飯田 倖鈴 -
4年生 世界にほこる和紙 10/30
- 公開日
- 2023/10/30
- 更新日
- 2023/10/30
学年の様子
「世界にほこる和紙」という説明文の学習が始まりました。
初めて読んだ感想を、タブレットで交流しました。
無形文化遺産に登録されたことや、洋紙より破れにくいことなどを知り、子供たちは驚いていました。
明日から、文の構造に着目して、深く読んでいきます。
筆者の主張に気付けるか、楽しみです! -
学校花壇チューリップの球根植え 10/30 462号
- 公開日
- 2023/10/30
- 更新日
- 2023/10/30
校長室
学校には、1学級に1つ花壇があります。今日は、すみれ級・わかば級・ふたば級合同の球根植えを実施しました。先日、今まで咲いていたマリーゴルドやサルビア等を抜き取り、肥料を撒いて土壌を整えておきました。今日は、チューリップの球根とパンジーの苗を植え込みました。子供たちは、担任の先生が指示されたとおりに丁寧に作業を行っていました。春に綺麗な花を咲かせるのが楽しみです。
チューリップの球根と言えば、この土日で我が家の球根植え込み作業を行いました。私は、高級品種の「ハウステンボス」が好きで「となみ球根まつり」で事前に購入しておきました。この花は、ピンク色で花弁がちりちりの特徴を持っています。この球根は、プランターに植え込みました。残りの花壇には、毎年開花後に掘り起こしておいた球根を植え込みました。毎年、球根を購入しているので球根は増える一方です。花壇には、5cm間隔ぐらいに植え込むことになりました。それはそれで、チューリップが群がって開花するのでチューリップ畑として美しいかなと思っています。
私は、球根の掘り上げ方と保存方法はネットで紹介されている方法を守っています。
1.花が咲き終わる
2.葉っぱを残して花の茎だけを切り取る
3.薄めた液体肥料を月に3〜4回与え、乾燥する前に水やりをする
4.葉が黄色くなって、枯れはじめたタイミングで球根を掘り上げる
5.球根の上で茎をカットして、分球した球根を1つ1つ分ける
6.表面の土をキレイに落とし、ネットなどの通気性のよい袋に入れる
7.次の植え付けの時期まで、風通しの良い場所で日陰干しにする
子供たち自身にも球根の掘り上げと保存を体験してもらいたいなと思っています。
-
城端線・氷見線ワクワクする電車に 10/27 461号
- 公開日
- 2023/10/28
- 更新日
- 2023/10/28
校長室
23日に両線の運行主体を将来的にあいの風とやま鉄道へ移管することで関係機関が正式合意し、県と沿線4市、JR西日本、あいの風とやま鉄道で作る検討会が議論を進めておられます。
鉄道は、高校生や高齢者にとって日常生活に必要不可欠な足です。個人的には3つの意見を持っています。
1つ目に鉄道が運賃収入で自立経営できるとの考え方は、東京や大阪中心の発想であり、世界的に見ても特殊な考え方のようです。世界的には、図書館や警察署のように「鉄道は公共サービス」というのが常識なようです。したがって、「鉄道会社」を助成するという趣旨ではなく地域の足という公共サービスを支えるローカル線に投資するとい発想の転換が必要だと思います。
2つ目はICチケットの導入です。先日東京へ出張しました。首都圏内はどの鉄道会社も腕にはめたスマートウォッチで、改札口を通過することが出来ます。切符を購入する手間を省くことが出来ます。また、富山駅では2台の長距離切符購入自販機に長蛇の列が出来ていました。「いくら新架線の移動が速くてもこれでは?」と感じました。私は、ネット予約しておいたものを自動発券機で出してもらうだけだったので待たなくて済みました。是非ともローカル線にも導入をと思っています。
3つ目はワクワクする新型車両の導入です。都会の電車は、高速で静かで揺れも少なく外気を汚しません。車体の外観もとても格好いいです。以前に富山駅から岩瀬駅までセントラムに乗ってみたことがあります。実に快適で家族でもう一度乗ってみたいと思いました。子供たちがワクワクするような外観はとても重要です。当検討会で4つの案(写真 富山新聞掲載 左上から時計回りに電気式気動車、蓄電池駆動電車、水素車両、ハイブリッド気動車)が示されたようです。
城端線・氷見線再構築案の今後の協議を興味深く見守っていきたいと思います。
-
4年生 本番に向けて 10/27
- 公開日
- 2023/10/27
- 更新日
- 2023/10/27
学年の様子
体育の時間では、来週のチャレンジランニング大会に向けて持久走の練習をしており、水曜日から実際のコースを走っています。距離が長いので、とても辛そうな顔をしていますが、全員最後まであきらめず走っています。
-
1年生 お弁当の日 10/27
- 公開日
- 2023/10/27
- 更新日
- 2023/10/27
学年の様子
1年生の昼食の様子です。
今日は、庄南仲よしウォークの予備日で、お弁当の日でした。
4限が終わると、「弁当だ!」と嬉しそうに準備をはじめました。
いつも以上に笑顔いっぱいの昼食タイムとなりました。 -
学校だより
- 公開日
- 2023/10/27
- 更新日
- 2023/10/27
お知らせ
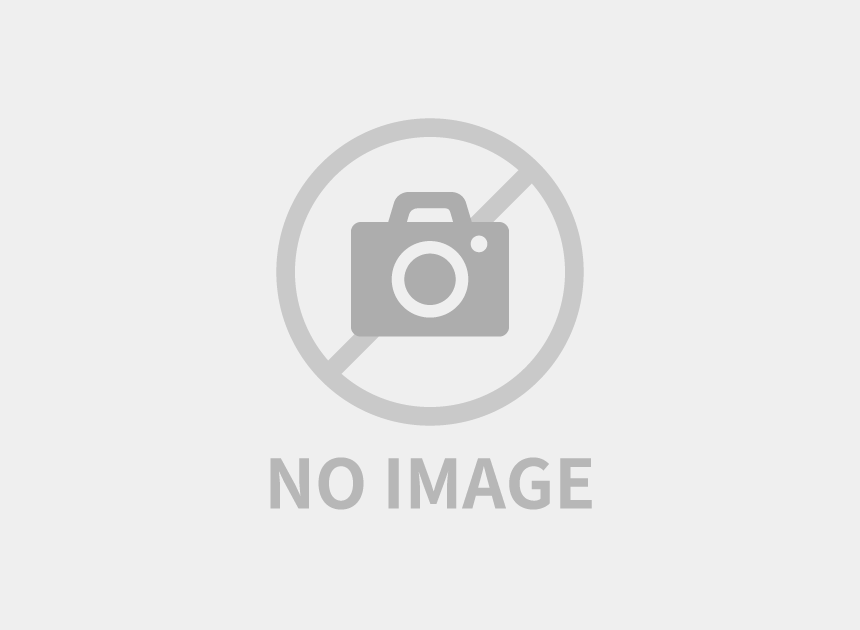
学校だより10月号をアップしました。配布文書欄をご覧ください。
-
江戸と明治の生活はどのように変わったのだろう? 6年生 10/26
- 公開日
- 2023/10/26
- 更新日
- 2023/10/26
学年の様子
6年生の社会科の学習の様子です。江戸と明治の写真を比較して、生活場面のどこが変わっていったのかを読み取っていきました。明治の写真から、服装、交通、街並みといった視点でどれも現代に近い生活になってきていることを理解しました。授業の終わりには、子供たちからは「江戸時代が終わったのはどうして?」「ここまで生活が進歩したのは何でだろう?」と自分なりの疑問をもつことができました。ここから自分の課題をもとに、学習を進めていきたいと思います。
-
5年生 校外学習 10/26
- 公開日
- 2023/10/26
- 更新日
- 2023/10/26
学年の様子
校外学習で、「イタイイタイ病資料館」「四季防災館」へ行ってきました。
「イタイイタイ病資料館」では、公害により病気で苦しむ人がいるだけでなく、その家族やそこで田を作る人も多くの人が大変な思いをすることがわかりました。子供たちは展示資料や映像資料、語り部さんの話から、イタイイタイ病の苦しさと今もなお続く大変な苦労と努力を感じ取っていました。
「四季防災館」では、地震や水害の恐ろしさを身をもって体験しました。また、話を聞いたり、消火器を実際に使ってみたりしながら、身を守る方法も学びました。地震体験では、揺れると分かっていても、予想以上の大きな揺れに戸惑う様子が見られました。
今回の校外学習で学んだことを、伝えたり意識して生活したりしていってほしいと思います。 -
「10月26日は柿の日」 10/26 460号
- 公開日
- 2023/10/26
- 更新日
- 2023/10/26
校長室
今日26日は、正岡子規が「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」の名句を詠んだ日とされ、2005年に「柿の日」に制定されました。全国的に栽培面積は減っていますが、美肌効果もある栄養満点の柿の人気は世代を超えて根強いです。
古事記にも記述がある柿は「国果」とも呼ばれ、日本を代表する果実です。渋柿を吊るし、寒風に当てて作る干柿は、しみ出た糖分が白く粉上になると食べ頃です。渋柿から劇的に変化した上品な甘さは和菓子の甘みの基準になったとされています。子どもにとっては塩味の効いたかき餅とともに冬の貴重な副食でした。
私が小学生の頃、台所で祖母がいつも渋柿の皮を剝いていました。皮を剥いた2つの柿をタコ糸で結び、納屋の軒下に設置されている竿に吊るしました。皮剥き作業を興味深く眺めていた私を見付けた祖母は、「お前もやってみるかい?」と言ってもう一本の包丁を渡してくれました。初めは、「そんな分厚く皮をむいてどうするんだい?」や「すぐ皮が切れちゃうね!」と言われていましたが、見様見真似で作業を進めていくうちにどんどん上達していきました。薄く一続の皮剥きが出来るようになりました。
そこで当時子供心に2つの疑問を持ちました。「あんな渋かった柿が寒風に当てるとどうして甘くなるのか?」と「スーパーで販売している干柿の表面はあんなに綺麗に白粉が吹いているのか?」です。今はネット時代なので、2つ疑問をネットで調べてみました。
果実は、動物に種子散布をしてもらうために、動物に好んで食べてもらえるような果実を作ります。しかし、種子がまだ発芽能力を持たないような成長段階の果実を食べられてしまうと、植物にとってはただの損失です。そのため、熟すまでは、渋みのあるタンニンで果実が食べられるのを防ぎ、種子が発芽可能な状態に準備できたころに、動物に好まれるような味に変化させます。見た目も目立たない緑色からオレンジ色に変化させます。したがって、渋柿も、実がジュルジュルに柔らかくなる頃には、タンニンが不溶性に変わり渋さが抜けます。つまり、甘柿の品種は、種子散布のベストタイミングより早く、タンニンの効力をなくしてしまった、うっかり家系といえます。
ここまでのお話から、甘柿はタンニンが含まれていないのか、タンニンが不溶化されているのか、どちらだろうと思われた方もいるかも知れません。実は、甘柿には、タンニンが含まれるものの、それが不溶性であるために渋みがない不完全甘柿と、そもそもタンニンをほとんど含まない完全甘柿の2種類に分けられます。
完全甘柿は、柿の実の成熟過程でタンニンの蓄積が止まるため、タンニン濃度が低く維持されます。これらの品種は、タンニンを蓄積する能力を欠損したDNA変異体です。不完全甘柿は、タンニンの蓄積は起こりますが、種子でアセトアルデヒドが生産され、タンニンとくっつきます。アセトアルデヒドとくっついたタンニンは不溶化し、食べても渋みを感じなくなります。
また、渋柿も2つに分けられます。完全渋柿は、種子があってもなくてもジュルジュルに柔らかくなるまで渋いままの品種です。不完全渋柿は、種子から生産されるアセトアルデヒドによって、熟柿になる前から、種子の周りの果肉の渋が抜ける品種です。つまり、渋柿は、種があってもなくても、熟柿になる前にはタンニンがほとんど不溶化されない完全渋柿と、種の周りの果肉のみが不溶化される不完全渋柿の2つに分かれます。
柿をアルコールにつけておくと、柿の実の中でアルコールがアセトアルデヒドに変わり、そのアセトアルデヒドがタンニンとくっつき、不溶化します。また、炭酸ガスを充満させたところに柿を入れておくと、柿が酸素不足になり、アセトアルデヒドが生成され、タンニンが不溶化します。干し柿は、皮を剥くことによって、カキ表面に皮膜ができ、果実の細胞が呼吸できなくなることにより、アセトアルデヒドが生成され、タンニンが不溶化します。
つまり、人が行う柿の渋抜きも、タンニンを取り除いたり分解したりしているわけではなく、タンニンを不溶化して、渋みを感じないようにしています。渋みがなくなると、甘みが感じられるようになります。渋抜きの処理前と処理後で甘みは変わっていませんが、渋みを感じなくなったため、甘く感じるようになります。
また、2つ目の疑問の「干し柿の表面が白くなる」のは、寒さと空気が乾燥していることで柿の糖分が染み出て乾燥し、表面に白い粉として残るからだそうです。福光東太美地区は、干柿の産地です。冬に寒い乾燥した風が医王山から吹き下ろし絶妙に柿の糖分を染め出していると聞いたことがあります。
柿の木は、我が家にもあります。この機会に、日本を代表する果実「柿」の賞味の仕方を見直してみたいと思います。
-
R1 飲用開始! 10/26
- 公開日
- 2023/10/26
- 更新日
- 2023/10/26
学年の様子
今年度も、「砺波市×R-1 街の強さひきだすプロジェクト」ということで、R1の飲用が始まりました。
子供たちは、「おいしい!」と顔をほころばせ、飲んだ後は元気にグラウンドへ飛び出していきました。
なぜ小中学生に明治R−1?
その秘密は「街の強さひきだすプロジェクト」サイトで
https://www.city.tonami.lg.jp/info/63746p/
-
4年生 チャレンジランニング大会に向けて! 10/25
- 公開日
- 2023/10/26
- 更新日
- 2023/10/26
学年の様子
大会のコースを走ってみました!
日頃の5分間走の成果が出て、とてもよい走りをしていました。
本番に向けて、燃えています!
応援よろしくお願いします。
後半のティボールも白熱の試合でした。 -
3年生 アルファベットが分かったよ 10/25
- 公開日
- 2023/10/25
- 更新日
- 2023/10/25
学年の様子
3年生は外国語活動でアルファベットについて学習しました。
アルファベットのカードをA〜Zまで並べる活動では、みんな真剣な表情でした。
ニコール先生がBやV、GやZ等の似ている発音を丁寧に教えてくださったので、子ども達も発音したり聞き取ったりするのが上手になりました。 -
クマの被害人数 17道府県で153人に 10月は43人で先月超える 10/25 459号
- 公開日
- 2023/10/25
- 更新日
- 2023/10/25
校長室
NHKが各地域局の取材を通じてまとめたところ、ことし4月以降にクマに襲われるなど被害にあった人の数はこれまでに少なくとも17の道府県で153人にのぼっているそうです。このうち10月に入ってからは連日被害が相次ぎ、19日までに44人とすでに先月1か月の38人を大きく上回っています。
ことし4月以降のクマによる被害を道府県別にみますと、秋田で52人と全体の3分の1以上を占めているほか、岩手で36人、福島で13人、青森で10人と東北地方を中心に相次いでいます。 このほか被害が出ているのは、長野で10人、新潟で5人、北海道で4人、山形で4人、富山で4人、岐阜で4人、群馬で3人、宮城で2人、石川で2人、福井で1人、三重で1人、京都で1人、島根で1人となっています。
また、10月に入ってからの被害を見ますと、19日までに、秋田で24人、岩手で9人、青森で3人、富山で2人、石川で2人、北海道で1人、群馬で1人、福井で1人、長野で1人となっています。東北で秋田や岩手を中心に被害が相次いでいるほか、北陸の富山、それに先月まで被害が出ていなかった石川や福井でもけがをする人が出るなど被害が拡大しています。
被害にあわないためにはクマの被害にあわないためにどのようなことに気をつければいいのでしょうか。クマの生態に詳しい石川県立大学の大井徹特任教授の話によると
【クマを寄せつけないために】
まずはクマを人の生活圏に近づかせないための対策です。
クマは餌を求めて人里に近づいてくるとみられます。柿やクリなどを好んで食べるため、実った果樹などをそのまま放置しておかずに収穫するなどしておいてください。また、生ゴミやペットの餌を屋外に出しておかないようにしましょう。さらに、やぶを刈ったりしてクマが身を潜めやすいような場所を減らすことも大切です。 また、住宅街に迷い込んだクマがパニックになって建物に入り込んでしまうこともあります。住宅や物置の戸締まりもしっかりとしておくようにしましょう。
【クマと遭遇したときには】
クマに鉢合わせしてしまったときにはどのように行動すればいいのでしょうか。まずは落ち着いてクマのようすをしっかりと観察するようにしてください。すぐに向かってこないようであれば、ゆっくりと後ずさりしてその場を離れるようにしてください。クマは逃げるものを追う習性があるため、背中を向けて走って逃げようとしてはいけません。万が一、襲いかかられてしまったときにはうつぶせになるなど防御姿勢をとり、首や腹などを守って致命傷を避けるようにしてください。 とのこと。
昨日の庄南なかよしウォークでは、班長にクマ鈴替わりの大きな鈴を持たせました。一昨日は、南砺市城端小中学校付近の山田川沿いに日中熊が出没し、家族による引き渡し下校となったようです。いつまでクマ出没に悩まされるのか。情報を得た時は、地域の皆さん、PTA役員の皆さん、教職員に一刻も早く情報を共有し被害を回避したいと思います。
-
庄南仲よしウォーク 10/24
- 公開日
- 2023/10/24
- 更新日
- 2023/10/24
学年の様子
秋晴れの中、庄南仲よしウォークで今年度は太田地区に行ってきました。地域のよさや同じ班の友達のいいところを見付けながら、楽しく歩いてきました。学校に戻ってからは、班のみんなと交流活動をしました。(校長室参照)
-
庄南なかよしウォーク! 10/24 458号
- 公開日
- 2023/10/24
- 更新日
- 2023/10/24
校長室
快晴の下、庄南なかよしウォークを実施しました。今年は、太田地区を散策し「太田体育館」「専念寺」「多難橋」「万福寺」「土改園」でオリエンテーリングを行います。オリエンテーリングでは、担当の先生が出題される問題に班員で回答していきます。この活動のねらいは、
1 庄南校区の自然や産業、施設、名所等を見たり聞いたりする活動を通し て、地域を 理解し、地域に親しみをもつことができるようにする。
2 長距離を歩き通すことで達成感を味わうとともに、公共場所の使い方やマナー、交通安全に対する安全意識を育てる。
3 異学年や地域の人に励ましてもらったり協力し合ったりすることで、笑顔で「心からありがとう」の気持ちを実感したり表したりできるようにする。
オリエンテーリングに使用する2つのお寺をご挨拶に訪問しました。一方は、奥さんが境内の草むしりをしておられ、「校長先生、今日遠足に来られると聞いておりながら今頃草むしりしていてすいません。」と言葉を掛けていただきました。もう一方のお寺は日中、勤めに行っておられるようで、施錠されたままでした。子供たちには、「午後や土日の自分の地域の様子は分かっていたと思うのですが、皆さんが学校に行っている時間の様子は今日初めて分かったんじゃないですか?」と投げかけてみました。
子供たちが縦割りの班で歩いている様子から、上級生が1年生の子供に「荷物重そうだから持ってあげようか?」と優しく声掛けをし、荷物を運んであげている姿や同じ声掛けをしても、1年生が「有難う。でも大丈夫!」と返して最後まで重い荷物を担いで歩き切る姿が見られました。
天候にも恵まれ、事故や体調不良者も無く無事に有意義な1日を過ごすことができたと思います。3つのねらいは、ほぼ達成できたのではないでしょうか。今後の学校生活に生かして欲しいです。

